学研の先生の研修会に学ぶ読書感想文の書き方
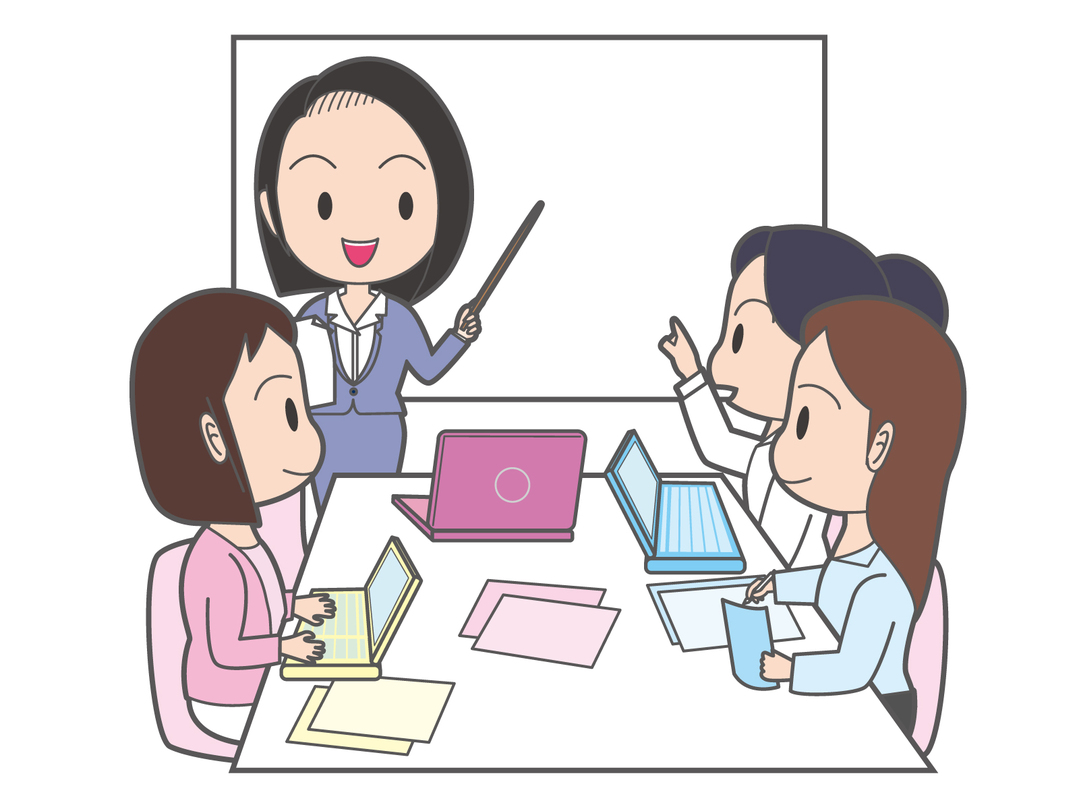
学校の夏休みの宿題で「読書感想文」が出て、大変だな~と思っている生徒さんも多いのではないかと思います。
読書感想文て大変ですよね。気持ちは分かります。だって私も、学研の指導者研修会で、最後に大勢の先生の前で感想発表をしなくちゃいけない事がたまにあるからです。
私は、この感想発表が苦手なんです。
大勢の人の前で喋るのも苦手ですし、そもそも感想って、ある程度ちゃんとした事を言おうとしたら、色々頭を使わないと出て来ないじゃないですか。
研修会終了間際の私の感想など、バカ正直に言ってしまえば
「色々聞いて疲れちゃったので、午後の授業に備えて昼寝をしたいと思います。」
という事になりますが、大の大人が、そんな事を感想発表で言うのは、人として失格だと思います。
感想文を書く時に、これと言った感想が思い付かなかったからといって
「頑張って読んだけど、感想なんて思いつかなかったです。しいて言えば脳が疲れました。疲れを癒すために、飴でもなめたいと思います。」
などと書いてはいけなのと同じ事です。
そんな事じゃダメなのです。当たり前じゃありませんか。
小学生だって中学生だって、そんな事は百も承知だから(現段階で、この認識があるのであれば、まぁまぁ真っ当な大人になれるのではないかと思います。読書感想文というのは大人の階段を上る第一歩なのです。)
「読書感想文どうしよ~」
と悩むわけです。
じゃあどうすれば良いかって話なんですが。
学研教室の、特にゼミ研と呼ばれる研修会の場合、感想発表に関しては、事前に頼まれる事のほうが多いのです。(急に感想を言ってくださいと振られる事もありますが、心臓に悪いので止めて欲しいと思います。)
研修会の最初のほうで
「今日の感想発表は◯◯先生にお願いします。」
みたいな感じで指名されます。
で、私は指名された時と、そうでない時では研修会の聞き方が違うのです。
具体的にどう違うかといいますと。
私は、感想発表をしない研修会の時は、ただただ自分の感覚のみで他の先生の話を聞いています。
「素晴らしい意見だな。」
と思えば、
「うちの教室で実践してみたらどうなるかな~?」
などと、可愛い生徒さん達の顔を思い浮かべながら想像し、
「お!うちの教室でも出来そうだな!真似してみよ~。」
とか
「良い意見だと思うけど、うちの教室だと、ちょっと実践出来ないかな~。(先生の方針とか生徒さんのタイプとか人数とかアシスタントさんの有無とか、色々ありますからね。)」
とか
「うちの教室だったら、こういうふうにアレンジしたらもっと良いかな~?」
とか、めちゃくちゃ個人的な事を、結構忙しく頭の中で考えています。
本を自由に読む時っていうのは、こんな感じで良いのです。
ただただ自分の感覚を解放して、感情移入してみたり(この場合は、感想文は書きやすいと思います。)
「なんかつまんないな…。全然感情移入も出来ないし…。」
と思ってみたり。それで良いんです。
結果、これと言った感想が思い浮かばないなんて事もあるわけで。
私は、それでも良いと思っています。
私も正直な所、研修会で
「色々素晴らしい意見は出たけれど、どれもそのまま私の教室で実践するのは難しいな。」
と思う事も、たまにはあるのです。(そんな時に、いきなり感想を言えと振られたら、どんだけ私が動揺するかお分かりでしょうか。)
でも、感想を言うのであれば、それではダメな時もあるわけですよ。
なので、感想発表に指名された時は、ひたすら感想を言う為に、他の先生の話を聞きます。
自分の教室で実践出来そうかとか、そういう事は考えません。(そういう事は意見のメモを取っておいて研修会終了後に考えます。)
とりあえず、自分の教室で実践出来るかどうかは置いておいて、単純に
「凄いな。」
と感心した事とか、
「これは多分、多くの先生の共感を得る意見なんじゃないかな?」
と思った事とか、とにかく感想で言い安そうな意見を、ひたすらメモに残していきます。
で、ディスカッションが終わった後の、1分くらいの時間で、バーと書き出した意見を見て、
「これとこれとこれで行く。」
と◯をつけ、それを横目で見ながら
「◯◯先生の意見は生徒さんの達の成長に役立つ素晴らしい物だと思いました。」
とかなんとか発表するわけです。
「感想発表」ではありますが、あまり自分の感情は入れません。
入れちゃうと一発勝負の研修会では
「素晴らしい意見ばかりだったけど(これは本当です。)私が実践できると思った(要するに共感した)意見は一つもありませんでした。」
などという恐ろしい結果になる可能性も絶対に無いとは言いきれず、そんな事になったら、取り返しがつかないからです。
しかし、読書感想文の場合は、研修会と違って一発勝負ではありませんから、読む本を選べるのであれば、まずは
「これなら感想が浮かびそうだな」
という本を選ぶ所から始めたら良いと思います。
で、ただただ感情の赴くままに読んでみて、感想が出てきたら、それを書いたら良いのです。
しかし、作品を選べない、または選んだつもりだったのに、読んでもこれと言った感想が浮かばなかった場合は、ただただ本を読むのでは無く
「感想を書くぞ!」
という強い心づもりで読んでみてください。
それでも、自分にピンとくる感想が出なかった時は、視点を変えてみてください。
研修会で感想発表を任された時の私は、自分に軸を置いて話を聞いていないんですよ。
では、どこに軸を置いているかというと
「多くの先生」
に置いているという事になります。
「多分、多くの先生はこの意見に共感するんだろうな。」
とか
「これは真似したいと思う先生が沢山いるかもな。」
とか、そういう視点で聞いています。
感想文も、どうも自分の感想がピンと来ないと思ったら(名作に誰もが心打たれるとは限らないのです。)多くの人が感動する場面てどこなんだろう?とか、そんな視点で読んでみるのも良いかもしれません。
「多くの人」だと、なんだか壮大過ぎて分からないという事であれば「自分のお母さんだったら」とか「友達だったら」とか身近な人の気持ちになって読んでみるのも良いかもしれません。
そうやって、どうにか感想を捻り出した経験が、大人になってから役に立つ事もあるかと思います。
少なくとも私は、数ヵ月に一回、未だに読書感想文(読書じゃなくて研修会だけど)を発表しなければならないという苦行にみまわれています。
どうか
「粗筋を書いて終わらせる」
などという事が無いように、どんな感想でも視点でも構いませんから、ちゃんと「感想」を書いた「読書感想文」を仕上げて欲しいと思います。
頑張ってください。私も研修会を頑張ります。
それでは、最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
2024年08月09日 Posted bymitsubachi at 13:24 │Comments(0) │国語 読書
※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。










